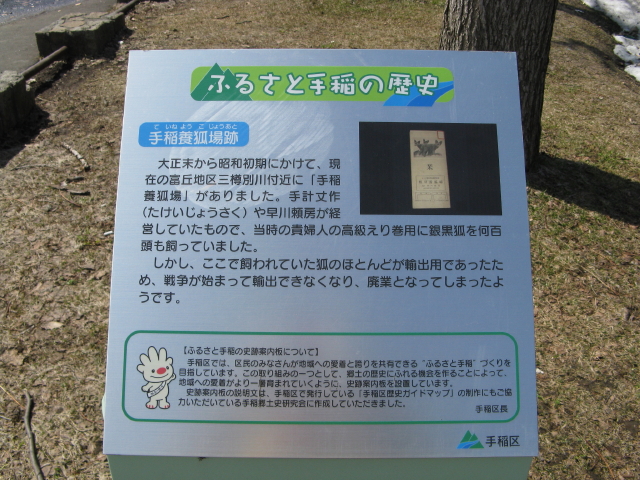| �����j�U�� |
|
�@�|�C���g �@�ȑO�A����j�ՃK�C�hHP�ɋL�ڂ���Ă����B���̔ԍ��́u������j�K�C�h�}�b�v�v�ɋL�ڂ���Ă����ԍ��B |
| 1.�y�얳�d�Ǝ������ | 2.���_�А_�`�a | 3.�k�_�y�쑐�Y�H��� | 4.��F�_�А� | 5.���Α� |
| 6.��x��̏��� | 7.���_�АՒn | 8.���u�ʓ� | 9.���z�R�I�z��� | 10.��̑�� |
| 11.�R���^�� | 12.���R���o�b�^�� | 13.���z�R���a�r�� | 14.�k���{��s��� | 15.���y��w�ɐ� |
| 16.���{�Ζ��������� | 17.�O�c�Ɉ�� | 18.�y�O���� | 19.�V��_�А� | 20.����� |
| 21.�����ِ� | 22.�ꕶ���ヌ���[�t | 23.���{�Ϗ�� | 24.�T���^���x�c�ʍs���� | 25.������������ |
| 26.�y��X���i���̓��j | 27.�Ύ�X�� | 28.�y�I�r�� | 29.�V�� | 30.�J���\�N�L�O�� |
| 31.�J�����\�N�L�O�� | 32.���u�J���L�O�� | 33.���u�_�ЋL�O�� | 34.���u�J��S�N�� | 35.�R���J��80���N�� |
| 36.�R���J��100���N�� | 37.����_�L�O�� | 38.���h�T�� | 39.������ϊJ��L�O�� | 40.����J���L�O�� |
| 41.���J��S�N�L�O�� | 42.�{�����n�� | 43.������ | 44.�{���n���ϐ��� | 45���.���n���{�� |
| 46.�R���n���ϐ��� | 47.�O�c�n���ϐ��� | 48.�k�����n����_ | 49.�x�u�n���ϐ��� | 50.�����H���W |
| 51.���̔� | 52.�u���X���^�v�� | 53.���ЋI�O�� | 54.�g�a�b�e���r�L�O�� | 55.�D�y�ԊJ�ʋL�O�� |
| 56.���{�����L�� | 57.�O�c�_��L�O�� | 58.���э�����Д� | 59.���K�ًL�O�� | 60.�h�̎� |
| 61.���_�Љ��{ | 62.���R�̎O�p�_ | 63.���p���_�C�X�q���b�e | 64.���̕v�w�� | 65.���L�O�� |
| ���ʐ^���N���b�N����Ƒ傫�ȃT�C�Y�ɂȂ�܂��� |
| �@1.�y�얳�d�Ǝ����꒡�ɐ��@���{��3��1����3�@�@<�f11.4.15> |
|
�@���݁A���R�~���j�e�B�Z���^�[�ɂȂ��Ă���B������o�����̎��܂ł͖ʉe���������B |
| �@2.���_�А_�`�a�@���{��2��3����4�@�@�@<�f11.4.15> |
| �@3.�k�_�y�쑐�Y�H����@���{��2��4���ځ@�@<�f09.12.28> |
|
�@�u�y�쑐�Y�H��v�͑����m�푈�̖����A���a20�N3���ɖk���i���݂̃z�N�����_�Ƌ����g���A����j�ɂ�莖�Ƃ��J�n���ꏺ�a24�N�ɏI�����悤���B �@������j�K�C�h�ł͒M��l�����̎��{�����ɁA�ԃ����K�̌������������ƋL����Ă���B�̌@�ꏊ�́A�͂����肵�Ȃ����A�ȑO�A�z�N�����̏Z��i���݂̃z�N�����V���b�v�j�����������ӂȂ̂��낤���B��������ƁA�_�ƒc�̂̃z�N���������ɓy�n�������Ă��Ă��s�v�c�ł͂Ȃ��Ȃ�̂����B |
| �@4.��F�_�А��@���{��2��5����12�@�@<�f10.1.30> |
|
�@��F�_�Ђ͒��y��قƃ}���V�����̊Ԃɉ��т铹�H�̉��ɂ������悤���B��F�_�Ђ͓��{�Ζ��k�C���������̎��_�������B�������͑���E��풆�ɃA�����J�R�̋�P�����B���{�R�̍��˖C����͈ꔭ�̋ʂ����˂���Ȃ������ƌ����B �@��F�_�Ђ͎��_�Ђɍ��J���ꂽ���A�Ύ�s�������̑�̎R���ɂ͐Δ肪�����Ă���Ƃ̂��ƁA�@�����ΖK�₵�����B |
| �@5.���Α�i�ʃy�[�W�@�D�y�~�G�I�����s�b�N��\�ցj�@���R�X�L�[��@�@<2011.4.27> |
| �@6.��x��̏���i���j�j�ՕW�j�@���2��1����5�@�@�@<�f09.12.8> |
|
�@���������C�Ȃ��ʂ��Ă������H�����Ɏj�ՕW���������B��ň͂�ꂽ����`���ƁA�r���a������B����̃C���[�W�͖������A����Ă��鐅���Y��Ȃ̂ŁA���̂��ق��Ƃ���B |
| �{���r���Ɩ��������̏���́A�Z���̎�@��Ŋ��������B �{�芰�Ƃɕۑ�����Ă����Õ����i�ደ���t�j����ǂ� �����ʁA����13�N�i1880�N�j�A�J��g���@��������� ���̂Ƃ킩�����B�y�삩�番�����A��ϐ�ɒ����ł���B ���@�B�Ȃǂ���Ȃ�����A�Z�����o�̊��̌����������B ���ꂢ�ȗ��ꂪ�����Ă����B�Z���ɂƂ��āA���̐��͐����p�� �ł���B����k��ɕs���������B�N�Ɉ�x�A�Z�������W���� ���|��Ƃɏ]�������B ���a30�N��܂ő������B �y��̎搅���́A���H�̊g���Ɩ��Ƃ̑����Ŗ��v�A���������� �ł��������ɖ��݂���A�����̖ʉe���c���̂́A�킸���ɂ��� �t�߂����ƂȂ����B ��l�̋�J���ÂсA���i�����p�����ƁA �����ɗ��j�j�ՕW�𗧂Ă��B �@�@�@�@�@�@�@�@2002�N�i����14�N�j3�� �@�@�@�@�@�@�����R���������i�ψ��� |
| �@7.���_�АՒn�i���j�j�ՕW�j�@���4��5����4�@�@<�f09.12.8> |
|
�@���x���j�ՕW�̖T��ʂ�Ȃ���T���B�ꏊ���Ԉ�������Ǝv���A��̉Ƃ̂���l�ɕ�������A���H�����ɂ���Ƃ����B�c�O�Ȃ������݂̂������B |
| �@8.���u�ʓ��@�����R�@�@<�f09.12.8> |
| �@�D�M�����ԓ��̗�������I�z��Ղ߂�B�܂������邩�ȂƁA�ӂ���Ȃ��玩�]�Ԃ�i�߂Ă���ƁA���Ōx�J����B�Q�ĂāA���[�ɔ�����B���ɁA���z�R�̒��ɂ͓���Ȃ��Ǝv�����A�Q�[�g�̕��ɏ���čs���ƁA�E���ɃR���N���[�g�̌����ՂƎv�����\��������B�������A�����֎~�̂悤�ŁA�������Ă���B�悤�₭�A�Q�[�g�ɓ������邪�A�����Q�[�g�Ɍ}������B �@���������ƁA�A�邱�ƂɂȂ邪�A�n�}�Ɏl�p�����a�r�Ǝv������̂��ڂ��Ă���̂ŁA��������Ă݂��B���̒r�͋��R�p�[�L���O�G���A���ɂ���Q�[�g�͂��邪�A�n���̐l�����͓��[��������Ă���悤���B�U���������Ղ�ǂ��ƁA�r�̏�ɂł��B��������́A�r���ǂ������Ă����B |
| �I�z��� | �Q�[�g���̌����� | �����Q�[�g | ���a�r |
| �@9.���z�R�I�z����@�����R�@�@<'03.2.22 ��ʐl�͓��ꂸ> |
|
�@�s�X�n��������]�ł���C�ɂȂ錚�������A�߂Â��Č��邱�Ƃ͏o���Ȃ��̂��c�O���B �@�s��̑��ɓ_�݂���Y�ƈ�Ղ͕ʃy�[�W�u���z�R��Ձv�ցt |
| �@10.��̑���@�����R�@�@<����> |
| �@11.�R���^�́i�ʃy�[�W�ցj |
| �@12.���R���o�b�^�ˁi�ʃy�[�W�ցj |
| �@13.���z�R���a�r���@��5��4�`5���ځ@�@<�f09.12.18> |
|
�@���z�R�̒��a�n���������ƌ��������Βn���ӂ����A���́A�ۈ珊�̉������V�т܂����Ă���B�y��̍������V�Ԃ̂ɂ͒��x�ǂ��̂��낤�B �@�y��ɂ́A�傫�Ȕr���ǂ�����o���Ă�����A�@�Ȓ��i���˂��傤�j�ʂ�ɖʂ����ꕔ���M�œ��ݐՂ�����A�����Č���ƒ��a�r�̕��͋C������B |
| �@14.�k���{��s�w�Z�i��s��j���@��3��1���ڕt�߁@�@<�f09.12.8> |
|
�@���a5�i1930�j�N���珺�a8�i1933�j�N�ɔ�s�ꂪ�������ƌ����B�������A�ʂ��Ă������Ȃ̂ŁA�����������Č��݂̊X���݂�����B |
| �@15.���y��w�ɐ��@���{��1��3���ځ@<�f11.4.15> |
|
�@�̂̎R�������̉w�ɂ͕���͂��������A�������A�w�ɂɓ��邱�Ƃ��o���Ȃ����p�҂ŊO�܂ň��Ă����B�J���̓��ɂ͑҂��Ă���̂���ς������B �@���̌�A�R�������̉w�ɂ͉��A�i���X�Ƃ��ĕۑ����A���̖T�ɁA�V�����w�ɂ��������B���̌�A����������ƕs�ւ��ƌ������ƂŁA���ւ����A���݂̎��w�ƂȂ��Ă���B |
| �@16.���{�Ζ��k�C�����������@�O�c1��11���ځ@<�f11.4.15> |
|
�@���݂́A���������斯�Z���^�[�ɂȂ��Ă���B |
| �@17.�O�c�Ɉ���@�O�c�����@�@�@<�f09.9.12> |
|
�@�O�c������������k�̐V����z����12��t�߂܂ŁA�ꕶ����̈�Ղ��������Ƃ����B���́A�q���B�̗V�Ԍ����ɂȂ��Ă���B |
| �@18.�y�O���i�n�ԓS���j���@�O�c�n��@�@<�f10.1.1> |
|
�@�Ύ�����i����44�����j�ɑ吳11�i1922�j�N���珺�a12�i1937�j�N�܂Ŕn�ԓS�����ʂ��Ă����B��Ԃ͐��F����ԔȂ܂ł�8�����������ƌ����B�y�́u���������v�ƓǂށB |
| �@19.�V��_�А��@�O�c10��11����1�@�@<�f10.1.1> |
|
�@�V��_�Ђ͑O�c�i���R�j�n��̎��_�ŁA���R�i����Օӂ肩�H�j���珺�a3�N�Ɉړ]�A�ȗ��A���a48�N�܂ő����A���̌�A���_�Ђɍ��J���ꂽ�ƌ����B |
| �@20.������@�����Ð�E�ݕt�߁@�@�@<'10.4.22> |
|
�@�����Ð�͐V��ɒ����ł���悤�Ȃ̂ŁA�E�݂ɓꕶ����̈�Ղ��������悤���B |
| �@�ԊO.�����Ð� |
|
�@�n�}�ł͔����Ð�͔�����̏㗬�Ɍ����邪�A������Ɍq�����Ă��Ȃ������B���̔��ɐV��ɒ����ł���悤�Ɍ�����B �@�����ŁA�����Ɠy�ǂ̌�������V��Ɍ������Ď��]�ԓ��H��H���Č����B |
| �@��������㗬��U������ƁA���R���^���ʂɌ����A�O�H�R�A�u�ΎR�A�����R�A�S����R�A����A�l�I�p���R�A���R�A����A���u�R�A�����R�A�t���R�ƌ��n����B�ꕶ����̐l�X�����̌i�F�����Đ������Ă����̂��낤�B |
| �����Ð�ƃ^���l�E�F���V���i���R�j |
| �@�y�ǂ̏��ɂ́A�J���̃c�K�C�����ǂ����ʂɕ����Ă����B�y�ǂ̌������ɂ̓p�[�N�S���t���y����ł���l�B�ň��Ă����B���]�Ԑ�p���H��H��ƁA����Ղ��߂���ƁA���H�ŏI���A���̓��H�ɉ˂��鋴�z���ɁA���R�������Ă����B�X�ɁA�����H��ڎw���Ɨg���ꂪ����V��ŏI����Ă����B �@�V��̍��݂ɓn���āA�y��̍����n�_����g���������B��������|���v�A�b�v���A�V��ɒ������悤���B |
| �J���̃c�K�C | ���R | �g����ŐV��� | �V��ɒ��� |
| �@�n�}�ł͔�����̏㗬�����A������Ɍq�����Ă��Ȃ������B����͐V��Ɍ������Ă���悤�Ɍ�����B�V���y�삪���C�����O�́A�y��̖k�Ɏc�鏬�삪������̏㗬�������̂ł͂Ǝv���B�����Ð�͕s�v�c�Ȑ삾�����B |
| �@21.�����فi����j�Ձi�ʃy�[�W�ցj |
| �@22.�ꕶ����L�O�����[�t�@�x�u3��6����1 �x�u����c�n�@�@�@<�f0910.04> |
|
�@��\�l�����ʂ�̎O�M�ʐ�E�݉����̓���o��ƁA�x�u����c�n������A���ԏ�ɖʂ���ǂɃ����[�t��������B |
| �@���ԏ�̒��ɓ��点�Ē����A�����[�t�����グ�v���[�g��ǂށB����ȏ��ɓꕶ�l���������Ă����Ƃ͋������B |
| �����A�O�M�ʐ�̐�ӂŁA��2500�N�قǐ̂̓ꕶ�y�� ���������@����܂����B���̐́A�ꕶ�l�����͊L�� �̎������߂Ď��̎R�������߂����Ă����̂ł��傤�B �����[�t�̃f�U�C���́A�ꕶ�y��𒆐S�Ɏ��̎R�R�� ���ƌ��Ɛ��̗�����C���[�W���܂����B |
| �@23.���{�Ϗ���@�x�u3��7����1�@�@�@<�f16.4.4>�@<�f11.4.15> |
|
�@���{�Ϗ�́A���݁A�x�u��܂ƌ����̋ߕӂ������悤���B �@�����̕Ћ��ɂ͉�����ݒu�i�ȑO�͌��t�����Ȃ������j���ꂽ�悤���B |
| �@24.�T���^���x�c�ʍs�����@�x�u2��5����2�@�@<�f11.4.15> |
|
�@�T���^���x�c�ʍs���́s�u�͐�V�쐅�n�@�O�M�ʐ�i����ׂ���jSantarubetsugawa River�@��̖��̗R���@���̂̓A�C�k��́u�T���_���b�P�v�܂��́u�T���^���V�L�q�v(�Ȃ�ŃV�J��~�낵���Ƃ���̓�)�B�k�C���t�̊Ŕ̉˂���t�߂ɂ������悤���B �@���́A�R���N���[�g�̉͐삾���A�̂͂ǂ�ȉ͐삾�����̂��낤�B |
| �@25.�����i������j���������@�x�u2��6����3 �@�@<�f09.8.20> |
|
�@�T�C�N�����O�̋A�蓹�A�������i��\�l���E���ʁj�����Ɍ������A�u�O�M�ʐ�v��n��ƁA���������Ă���̂����ʂł��Ȃ��������̖和������B �@�ǂ�����Ɓu�����������v�Ə�����Ă���悤�������B�������A�������ォ��؎������Ă����H��ȂƎv���B �@���̔��Α��ɂ͉����̕\�D���f�����Ƃ�����B |
| �@26.�y��X���i���̓��j�@���{���n��@���{��2��2����2�@�@�@<�f11.4.15> |
|
�@�y��X���ƌ���ꂽ��\�l�����ʂ�ɂ́A���̓��ƌ����Â����j���������K��������B���㓡�g������35�N�i1902�N�j�ɊJ�Ƃ����Ƃ����B |
| �@27.�Ύ�X���i�����Ύ�����j�@�O�c�n��@�@<�f10.1.1> |
| �@��18�̌y�O���ɓ��� |
| �@28.�y�I�r���i�y�I��@�V�쐅�n�j�@���n��@�@<�f11.4.15> |
| �@�����ʂƒM��ʂ�����鏊�ɁA�L�ꂪ����A���̈�p�Ɂu���y�I��v�Ə����ꂽ���j�������g������B���y�I��͑O�c��ƍL��ō������ĐV��ɒ������A�n�}�ł͉�����O�c��ɓy�I�삪��������悤�Ɍ�����B�L�ꂩ��㗬������ƑK���V��R���^���ʂɌ�����B�v�킸�A�����Ə㗬�����悤�Ɠ��H��n��ƁA�a�F�K�R�̉��̎��R���^���ʂɌ����Ă����B�L��ɋA���ė��āA����������ƁA�e���L��ɂȂ��Ă��邪�A���͐^���Ԃ������B |
| ���j�������g | �L�ꂩ��㗬 | �㗬 | ���� |
| �@29.�V���@�O�c�E�V�����n��@�@<�f10.1.22> |
|
�@�V��͒�K�Ő����������悤�ɁA�͌�����i�q�^���[�Ɍ������Đ^���������тĂ���B�͌��͏��M�s�ʼn�ꂽ�������ɕ����Ă���B |
| �@30.�J���\�N�L�O���@31.�J�����\�N�L�O�� �@�@�@�@��R�~���j�e�B�Z���^�[�@�@<�f09.8.9> |
| �@�Δ�Q�̍����ɂ́u�J�����\�N�L�O�v�ƒ����A���ɂ͏��a��\�Z�N�㌎�O�������Ƃ���B��ł킩�������Ƃ����A���̔N��11���Ɏ�������ɂȂ����悤���B �@�E���ɂ́u�J���\�N�L�O�v�ƒ����A���̉��ɖk�C���̕����������Ă��邪��ǂł��Ȃ������B���̗��ɂ͑吳�\�N�㌎�O�������Ƃ���B����ɂ��Ă��A9��3���͎��ɂƂ��ďd�v�ȈӖ��������̂悤���B |
| ���\�N�L�O | �� | �\�N�L�O | �� |
| �@32.���u�J���L�O��i30���N��j�@33.���u�_�Ќ䑢�c�L�O��i90���N��j �@34.���u�J��S�N���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���u�_�Ћ����@�@<�f09.10.19> |
| �@���u�_�Ђ̋��������A�{�a�Ɍ������ƍ��Ɂu���u�J��S�N��v�A�E�Ɂu���u�J���L�O��v���������B�J��S�N��ɂ͔蕶�������Ă���B |
| ���u�_�� | ���u�J��S�N�� | �蕶 | �J���L�O�� |
| �@�@�@�@��@�@�@�� �I�X������j�͎��Ƌ��ɗ��ꋎ�� �����\���N���̒n���u�͍L���� �����S��蓿�i�ߏ����O�\�Z�˂� ���A�Ɏn�܂��c�����т��[�n�̂��� �n�ɐ��ҒB�͉���ȗ��z�̂��ƊJ ���ɒ��葊������Q��ЊQ�ɉЂ� ����Ȃ���䅓��������������] �S�N�@�������ɐ��ߎw��s�s�D�y�� ���ɂ����Ă��̔ɉh���q���ɓ`���X�� ���i���邱�Ƃ��@䢂Ɂu���u�J�� �S�N�L�O��v������������̖� �@�@���a�\���N�㌎�g������ |
| �@�J���L�O��̉��ɂ͑吳��N�㌎�ƒ����Ă���B���u�_�Ђ̗R��������ǂ�ŁA���c�L�O��Ɍ������Ɓu���u�_�Ёv�̖��̉��Ɂu���u�J���X�O���N�������@���u�_�Ђ����{�@���a48�N9���g�������v�Ɨ��ꂩ�����������ǂݎ���B��������͐��C�Ɛ��u�s�X���L�����Ă����B |
| �J���L�O��̉� | �R������ | ���u�_�Ќ䑢�c�L�O�� | �C�Ɛ��u�s�X |
| �@�@�@�@���@�u�@�_�@�� �@�Ր_�@�V�Ƒ�_�@�L���_ �@�@�@�@��ȋM�_�i�卑�喽�j �@�����\���N�L���������S����\�Z�˂̓� �B�ɂ�萯�u�̊J��͎n�܂�A���̌�A�R���� �x�R���y�ѐX������̈ڏZ�ɂ�葺�����` ���������Ɏ��� �@�����m��ʌ����̒n�̓��A�ɐ�Z�ҒB�� ��y�������S�̂�菈�Ƃ��Ė�����\�N �����u��O�Ԓn�ɏ��K���������������� ��������Ր_���Ă��đ����̈��ׂƔ��W�� �F�O���� �@�����l�\�ܔN���ݒn�A�吳��N�㌎�J ���L�O��Ƌ��ɓ�Α���̏������������_��� �ڑJ �@���a�l�\���N�H�䑢�c�̋V���N�����q�ꓯ �S�������{�N�㌎�v�H �@���̌c�����L���ׂ��ڑJ�O�̏��Ђ̑���� ����������㐢�Ɉ₷����̂ł���B �@�@�@���a�l�\���N�㌎�g�� |
| �@35.�R���J��80���N�L�O���@36.�R���J��100���N�L�O���@�@<�f09.11.3> |
| �@�R���_�Ђ̓����ɂ͎R���J��80���N�L�O���100���N�L�O�肪����Œ������Ă���B80���N�L�O��̗��ɂ͏��a�O�\�ܔN�\�ꌎ�����ƒ����A100���N�L�O��ɂ͔蕶������A���ɂ͔N�\�������Ă���B |
| �R���_�� | 80�N��100�N�� | 100�N��̔蕶 | 100�N��̔N�\ |
|
|
| �@37.����_�L�O���@�O�c������ف@�@�@<�f09.9.12> |
|
�@��ْ��ԏ�̕Ћ��Ɂu����_�L�O��v�ƒ���ꂽ�Δ肪����B����̔蕶�͉���������Ă����̂��킩��Ȃ����A�Δ�̉�������Ə��a�\��N�������݂Ƃ���B���A�}�b�J�T�[���s�����_�n����ȑO�̂��Ƃ̂悤���B�@ |
| �@38.���h�T���@��ϋL�O��ف@<�f09.11.26> |
|
�@��ق̑O��Ɍ��Ă��Ă���̂ŁA���l�̉Ƃ̒�ɓ���悤�ŋC�����������A�f���l�e�������A�ʐ^�����B�点�Ă��������B �@��̌�ɂ͏��a59�N5�������ƒ����Ă����B |
| �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�Ɓ@�@�́@�@���@�@�v �@���̒n��́@���_�y�ѐ������̂Ƃ�����Ɣ_�Ə\���˂Ɩ������Ɗ�����Ђ̌o�c����q�ꓙ ����Ȃ�s�s�ߍx�^�_�ƒn��Ƃ��āA����Ȃ�_�Ɛ��ʂ�w�i�ɏ����Ȕ��W�𑱂��Ă����B �@�������Ȃ���A���̒n��̕t�߂ɍH�ꂪ�������Ō��݂���A�n�����̋��ݏグ�������Ȃ����� �Ƃ���A�n�����ʂ��ɒ[�ɉ�����Ƃ���ƂȂ����B���̂��ߑ��ʂ̐���K�v�Ƃ��闏�_�o�c������ �ƂȂ�A�_�n���藣���_�Ƃ������Ă������B���̌��ʁA�}�㕪�M�ɂ�镪���]�����s�Ȃ�ꂽ�� �Ƃ���A���̒n��̏����̔��W�ɑ傫�Ȏx��������������ꂪ�����A�ꕔ�L�u�̐S�ɂƂ��鏈�� �������B �@���̂悤�Ȑ܂�̏��a�l�\���N�\�ꌎ�A�D�y�s����g���{�s�ɂ��y�n��搮�����Ƃɂ�肱 �̒n��̈�w�̔��W��}���Ă͂ǂ����Ƃ̊��߂��A�D�y�s�ƒn���W�҂Ƃ̋��c���J�n���� ���B���̌�A���a�l�\���N�ꌎ��\���Ɉ�ϊJ��������̔��������A�����ɂ킽��W�@�y�� �����҂̈ӎu�m�F���s�Ȃ��A���a�l�\��N�Z���Ɏ������̓��ӂ�����ꂽ�̂ŁA�D�y�s���ɑ� ���D�y�s�Ă��ˈ�ϓy�n��搮���g���Ƃ��Ă̐ݗ��F�\�����s�Ȃ��A���N������\���t������ ���Ă��̔F���B �@���̎��Ƃ̍H�����{�ɓ����ẮA�\�z�O�̓��n�Ղɑ������A�������H���͓r���ōH�@�̕� �X��]�V�Ȃ�����铙�ň��̋Ɍ����Ɏ���A�����̍����̂��߂Ɋ����̓w�͂��d�˂�ꂽ�B�� ���ē��{�o�ς��ᐬ�����ɓ���A���Z�������ߓ��̉e���������āA�g�������^�c�����ɍ��f�� ���B���̍���Ȏ��ɓ�����A�D�y�s�̓K�Ȏw���Ƒg�������y�ъe�����҂���v���͂��Ċ����� ��ǂ����z���A�����Ɏ��Ƃ̊���������Ɏ��������Ƃ́A�W�҈ꓯ�̑傫�Ȋ�тł���B �@�����ɈӋ`���鎖�Ɗ����ɓ���A���̎��Ƃi���㐢�ɓ`���A���̒n��A���̋��̌���� �����W���F�O���A�����ɔ����������B �@�@�@�@�@�@���a�\��N�܌��g�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�g���ݗ��N�����@���a�l�\��N������\�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�g�@���@���@���@�@�@�O���Z�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@�@�@�ʁ@�@�@�ρ@��Z�l�A��@�w�N�^�[�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���@���@�Ɓ@��@�@�@�Z�E�㉭�Z���E�����ܐ�~ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�y�s�Ă��ˈ�ϓy�n��搮���g�� |
| �@39.������ϊJ��L�O���@�k������ω�ف@�@<�f09.11.26> |
|
�@�\���H�̈�p�̒��ԏ�ɁA�n����_�≄���n���Ƌ��ɁA�ɉB���悤�Ɍ��Ă��Ă���B�蕶������Ƒ吳3�N�ɖk��������A�����悤�����A�k���Ƃ͉����̒n���Ȃ̂��낤���B |
| �吳�O�N��l�k���i�ق�����j��藈����Ă��̒n���̉��i������j�ƒ�� �䩁i�ڂ��ڂ��j���錴��D�Y�y�ɂ��Ēn��ዔ��i�����͂��j�Ȃ� ���a��N������U���S�˗��_���c�ފ����� ����Ɋ���䅓�i����Ȃ�j���ɂ����̒n��L���̒n�ƂȂ� �����ɐ�B�i�����j�̐h�^�i���j���Ái���́j�т��̔���������� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a��N����_ �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a�\��N���J����A �@�@�@�@�@�@�@�@������@�ȉ��ȗ� |
| �@40.����J���L�O���@���L�O�ّO��i����������21����3�j �@�@<�f09.8.20> |
|
�蕶�͔���Ă��Ĕ��Ǖs�\�����A�T�ɉ��������A�J����l�̋�J��������悤���B |
| �@�@�@�@����J���L�O�� ����4�N�A�����ˎm�Бq���\�Y�M���i���Ώ��j���k�C���J��� �����A���̉ƒ��i�Ɛb�j150��600�]�l���̋�����ɊJ��̓r�ɂ� ���܂����B���̂���50��241�l���@��5�N�ɓ��A�����̂��A���� �n�i����j�̑������ł���A���˂̒n�Ƃ����Ă��܂��B ���̔�́A����ɏW�c�ڏZ������l�����̋�S�ƊJ���̎���� �㐢�ɓ`���邽�߁A����V�O�Y��N��L�u�����N�l�ƂȂ��āA ����44�i1910�j�N11��3���Ɍ������ꂽ���̂ł��B �ׂ�̎��L�O�ق��V�݂��ꂽ���a42�N�ɁA�����k20���ڂɂ� �������@����_�Ђ̋������猻�݂̒n�Ɉڒz����܂����B �@�@�@�@�@�@�@�@����10�i1998�j�N10���@�@������� |
| �@41.���J��S�N�L�O���@���L�O�ّO��i����������21����3�j �@�@<�f09.8.20> |
|
����J���L�O��ƌ��������킹�ɁA�����Ă���B�����m���̊����̂����ŁA�P�������ɒ���ꂽ�莏���T�ɕt���Ă���B |
| �@�@�@�@��@�@�� �@��䢂Ɏ��J��S�N�� �}�����B���̎��ɓ��� ���n�̎����荡�� �܂Ő���ɘj���Č������� ��ƌ��̂ɂ��ލ���Ɋ� ������܂ʓw�͂��� �ɕ�����ꂽ��l��B�� ���ӂ̐������߂āA���̔� ���������A�Ȃ��ĉi���㐢 �ɓ`���邱�Ƃɂ����B �@���a�l�\�Z�N�l����\�� �@���J��S�N�L�O���Ǝ��s�ψ��� �@�@�@�@�@�ψ����@���ց@���O�Y |
| �@42.���n���@���_�Ё@���{��2��3����4�@�@�@<�f09.8.9> |
| �@������̗���ɂ͋��n���ƌ��R�_�Ђ̐Δ肪����Ō����Ă����B�Δ�̗��ɂ͏��a�\��N�������݂ƒ����Ă����B����ɖڂ�]������u�O�c�_���g�����U�ɂ�����@�������l�̎v����`���@���n���ֈԗ�̐�������V�����C���@������\�N�����g���v�ƒ���ꂽ�蕶���������B |
| ���n���ƌ��R�_�� | ���n�� | ���n���̗� | �蕶�j |
| �@ |
| �@43.�������@���_�Ё@���{��2��3����4�@�@�@<�f09.8.9> |
| �@���_�Ђ̓��傩�����ƁA����Ɂu������v���������Ă���B�߂Â��ĐΔ�̖{�̂����グ�A��O�ɍ���e�Ǝv����Ɏ��}���펀�ҔV��ƒ���ꉡ44���c5���18�����v238���̖��O�����܂�Ă���B �@���ɉ��ƁA��t�����l�B�̖��O�������Ă����B�ǂ�����ƌl�ȊO�Ɉ���Q�E�~���{�Ζ��E�O�c�_��̖��O������B �@���ɉ��Ɩ{�̂ɑ吳���N�����O�������ƒ����Ă����B�{�̗̂��ɂ͖{�̂����V�����蕶������u�I�����Z�S�N�L�O�v�ƒ����̌R�l15���̖��������Ă����B���̔蕶�͏��a�\�ܔN�����\�Z�������ƒ����Ă����B |
| ���_���� | ������ | ������{�� | ��t�����l�B |
| �@�ԊO.���R�_�Д� |
|
�@�R�`���̌��R�_�Ђ̔�ɂ͓��a�R�E�H���R�E���C�R�ƒ����ɒ����Ă����B �@���ɂ͔莏�����܂�Ă����B�ǂނƁA�l�I�ȐΔ�̂悤�ŁA�����͏��a51�N5��16���ƌ������Ƃ������B |
| �@44.�n���ϐ����@���{��2��2����2 �@�@<�f09.8.9> |
|
�@�y��X�����������{���̕��������i���̓����j�ɒ������Ă�����B |
| �@45.���n���{���@���3��5����1�@����ّO �@�@<�f09.12.8> |
|
�@����5���������̈�p�ɐ��������Ē������Ă��鋍�n���{�������t����B �@��̗��ɂ́u���a���Z�N�E���g���A�J��80���N�L�O�����v�ƍ��܂�Ă���B |
| �@46.�n���ϐ����@�R���_�Љ� �@�@<�f09.11.3> |
|
�@�R���_�Г����̉��i�������s���j�B��ԏ�Ɋω��l������킷�ƌ����Ă��鞐���������Ă���B |
| �@47.�n���ϐ����@�O�c7��11����1 �@�@<�f09.4.14> |
|
�@�O�c���w�Z�̓��H������Ŗk���ɂ���i����14�N9��22�������j�B |
| �@48.�n����_�@�k������ω�ف@�@<�f09.11.27> |
|
�@�\���H�̈�p�ɖɉB���悤�Ɍ��Ă��Ă���B�ڗ����Ȃ��̂ŁA�������ʂ��Ă����̂ɑS���C���t���Ȃ������B �@��̗�������ƁA���a�\�N�܌������ƒ����Ă����B �@�ׂ�̂����ɁA�Q�̂̉����n�����������A�Ԃ���������Ă����B�@ |
| �@49.�n���ϐ����@�x�u4��4����5 �x�u���@�@�@<�f08.11.28> |
|
�@�x�u���ɐΔ�������߂Â��ƁA�n���ω��������B�����l�\�ܔN�����������݂ƍ��܂�Ă����B |
| �@�ԊO.���n���{�ˁE��_���@��������Q�X�O�|�Q�T�V ����_�Г��@�@�@<�f08.4.9> |
| �@����_�Г��ɋ��n���{�˂�����i�吳9�N7�������j�B�_�͋�ǂŋ��Гa����ڐA�����Ƃ����B |
| ����_�� | ���n���{�� | ��_�� | �R������ |
| �@����_�Ћ��Гa�n �@�@�@�@�@�@�@�@��_�u��ǁv�ڐA ���̓x����_�Ћ��Гa�n�̒���̐X�̌�_�Ƃ��� �n��̗��j���������Ă������̋�ǂ� ���L�̒n���̐S����l�X�����[����܂����B ����_�Ђ̋��̔��W�������낵�Ă����u�����ؐl�v�̋�ǂ� ���̌�������i���ɂ���肵�Ă��������� �l����Ƃ���ł��B �@��[���^�Ҍ�F�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�����Z�N�\���g�� |
| �@50.�����H���W�i����҂傤�j�@���R�~���j�e�B�Z���^�[�@�@<�f09.8.9> |
| �@�y���ԏ�̉��ɂ͐Δ�Q������A�����������߂��ƌ�����������B�߂Â��Č���ƁA��ԑO�Ɂu�����H���W�v�Ȃ���̂��������Ă���B�Δ�̑���ɖ��ߍ��܂ꂽ���łɐ����������܂�Ă����B���̐����������ł͉����ɂ��������̂��͗ǂ�������Ȃ������B���ɉ��Ɓu���a���N���݁@�k�C���K�v�ƍ��܂�Ă����B���������݂����ƌ������Ƃ́A�����������̂��낤�B |
| ��Q | ���H���W | �v���[�g | ���� |
| �@�@�@�@�@�����H���W �@���̓��H���W�́A�k�C���y�ю� ��̓��H�̋N�E�I�_�Ƃ��āA�� �a���N�ɏ��߂Đݒ肵�����A���x �ɂ킽�钡�ɂ̈ړ]���z�ɂ��A ���a�Z�\�N�㌎�ɉ��߂āA���̒n �ɍČ��������̂ł���B �@�Ȃ��A���̌��W���A�����ނ� �k���\�x�l�\���̕�����S���\ ���[�g���̒n�ɁA�ŏ��̈ʒu�� �����Ă���B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�y�s |
| �@�ԊO.�y���ԏ��@���R�~���j�e�B�Z���^�[�i���{��3��1����3�j�@�@<�f09.8.9> |
| �@���R�~���j�e�B�Z���^�[�̒n�����̈�p�ɂ́A�u�y���ԏ�v������B�Ŕɓ\��ꂽ��������ǂݕ������ꂽ�q�Ԃ����肷��B���ɂ͒݊v��x���`���t���Ă����B�����Ȏԗւ����[���̏�ɂ������B |
| �y���ԏ� | ������ | �q�� | ���[���Ǝԗ� |
| �@�@�@�y��O���i�ʏ́E�n�S�j�̗��j �@�@�@�@�ݒu���ԁ@�吳11�N�`���a11�N �@�@�@�@�@�@�@�y��i���j�`�Ԕȁi�Ύ�j�ԁi8�����j �@�@�@�@�@�@�i���݂̐��F�쑤����Ύ�s�����O�j �o�@�@�� ����14�N��{�E�D�y�ԂɓS���������Ă���A���݂̑O�c�n�� �̗��_�A����̐��Y�i�ƐΎ�̏H���i���j�Ȃǂ̗A���E��� ���ԂƂ��Ĕn�ԓS�����g�p���ꂽ�B �����̔n�S�͎D�y�E��ˊԂ��^�s���Ă����D�y�O�����̕��� �@�������āA�y��O�������ݒu�������A���H��ʂ� �@���B�ɔ����āA�n�ԓS���̖������I��A��10�N�Ŕp�~�� �@��邱�ƂɂȂ����B�@�����͌y��̏ے��I�ȑ��݂ł������B |
| �@51.���̔��@���R�~���j�e�B�Z���^�[�@�@<�f09.8.9> |
|
�@�����A�u���v�ƒ���ꂽ�Δ肪���R�~���j�e�B�Z���^�[�O�ɂ���B�������ĉE���ɂ́u���w�J�w�S�ܔN�E���F��n����\�N�E�L�O�v�ƒ����A�������č����ɂ́u���E���a�\��N�\�ꌎ��\�O���@���F�������v�ƒ����Ă����B105�N�O�Ɂu�y��ȈՒ�ԏ�v���ݒu���ꂽ�L�O���ƌ������A���Ƃ����r���[�ŁA�����ɂ��邱�Ǝ��̂��s���R�ɂ܂�Ȃ��Ǝv���B |
| �@52.�u���X���^�v���@�������O��i���{��3��2���ځj�@�@<�f09.8.9> |
| �@�u�������w�Z�v�̑O������ƁA�Z��������낷���ɁA�����̃��j�������g�Ȃ̂��������3�{���̏�ɏ����Ԃ牺���Ă����B���łɉ�����������Ă��邪�A���Ǖs�\�������B���̌�ɁA�V�R�̐Δ肪�������Ă����B���グ��Ɓu���璺�ꊫ�50���N�L�O�@���a�\�ܔN�\�����v�ƒ����Ă���悤�����A���R�Ƃ��Ȃ��B���ɉ��ƁA���ł����߂��Ă��āu��t�ҁ@�j��V�N��d���v�ƒ����Ă����B��ɉ�荞��Ō��グ��Ɓu���X���^�v�ƒ����Ă���B���߂āA�w�Z��w�ɂ��Ėk�̑�n�Ɍ����Ă�������\���Ɣ[������B |
| ���j�������g | ���X���^�̔� | ���� | �y��V�N��d�� |
| �@��̖T�ɂ͌�������ގ��v�����邪�A�ߋ������ގ��v�͂��̐Δ�Ȃ̂ł͂Ȃ����Ǝv���B�ߋ��ɉ��������Ă��������Ƃ��o���Ȃ����A���������ނ͎̂Ⴂ�S�̒��̎��v�ł͂Ȃ����낤���B�u���X���^�i����ӂ��悤�j�v�̈Ӗ��͋��璺��Ƃ͑S�����W��������Ɍ�����͔̂߂����B���̂��Ƃ͏��w���ɂ��S�ɂƂǂ߂ĖY��Ȃ��ŗ~�����B |
| �@53.���Ёi����j�I�O���@���_�Ё@���{��2��3����4�@�@<�f09.8.9> |
|
���_�Ђ̎����Ԉ��S�F�����߂��̓y��ɐΔ肪����A�߂Â��Č���Ƒ��ЋI�O��v�ƒ����Ă����B �@���̔�́A���_�Ђ��D�y�_�Ђ̌y��y�q��������̑��Ђɏ��i�����L�O�Ƃ��Č��Ă�ꂽ�悤���B�����͑吳�Z�N������\�O���Ƃ���B |
| �@54.�u�g�a�b�e���r�����L�O�v���@���R�R���@�@�@<2010.7.28> |
|
�@�g�a�b�̃A���e�i�̌��~�n�ɂ͐Α���̖傪����A����Ɩ؉A�ɋL�O�肪�������Ă����B�蕶�͔����I���߂������߂��A����Ă��ĉ�ǂł��Ȃ�������������B���̓��e�́A��Ђ̎В��Ƃ͎v���Ȃ��V�ѐS������A���ł��S��ł��e������ �@��̌��ɂ�9���ڂɂ킽��A�H���W�̋L�q������̂ŁA���n�Ō��Ă��������B |
| ��������������������� ���R�ɂ̓��X������e�� ���F���o�v����@�~�͏� �]�̐Ⴊ�ς��芦���������� ���ԁ@���₱�̎R���ɂ͉� �w�Z�p�̐����W�߂������� �a���[�k�C�������e���r�� �M���������@�Z�\�ẴA���e �i���ނ��Ă���@����͐� �E���w�̑呗�M���ł��� �����Ă͗t�o�R�ƃX�L�[ ���[�̂ق��ߊ��Ȃ����� ���̎R�ɂ��̍H�����Ȃ��� |
�߂����͉̂����@����̓e ���r���M���Ƃ��Đ�D�̏� ��������Ă��閣�͂ł��� ���邩�甭�˂���d�g�͑S ���ɐL�т遜���͖k���ԑ� �эL���ٗ��K�當�ɓd�g�� ���B���Ă���@�R���̑��M ���݂͓��H���K�v�ł��� �܂��l���Z�ݑ��M�@�� ����ɂ͐��ɓd�C���Ȃ��� �Ȃ�Ȃ��@�����̂��� ��~�����邩�@�l�X�͂��� ��s�\�Ƃ������d�Ƃ��� |
���������������͊��R �Ƃ��ĎR�ɒ��݂������� �����ď��a�O�\��N�l���� �灜�\�N�̊Ԃɓ��H������ ���d�͐��݂̂Ȃ炸���M�� �����Ƃ��̓��O�ݔ��ꁜ�� ���������@���~�̌�ʂ� �m�ۂ��Ă��邱��𐬂� ���������͉̂����@�� ��͖Ȗ��Ȍv��ߑ�Z�p�� �ō��x�ɋ�g�����\���I�{ �H�ƒS���ҏ]�����ɂ݂Ȃ� ��s���̐��_�ł���@���� |
�čH���͖����Ɋ��������a �O�\��N�O���O�\������� �J�ǎ����s�����N�l����� ����{�������J�n�����@�� ���ĉi�v�Ƀe���r�d�g�� �˂������邠��낤�@��� ���͂��̍H�����ɂ߂ď� ���Ő�������эH���W�� �̎u�Ɋ��ӂ��@���M����i �v�ɍK����ƋF�� �@���a�O�\��N�����̓� �@���������@�������v �@�@�@�@�@�@���������� |
| �@�ԊO.1�@��ꍆ�X�[�p�[�X�^���X�^�C���A���e�i�@�@�ԊO.2�@�k��_�������� �@�ԊO.3�@���[�^���[�N���u�̔�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@ �ԊO.4�@���E�� |
| �@��ꍆ�X�[�p�[�X�^���X�^�C���A���e�i��1/2�̖͌^�Ƃ��̉��ɔ蕶��������Ă������A�]��ɋ߂Â��߂��Ă��܂����̂ŁA�S�i�͎B���Ȃ��������A��L�g�a�b�A���e�i�ʐ^�̉E�ɖA���Ċ�̗l�Ɏʂ��Ă���B�k��̉_�������͋n�ɂȂ�A�和��������Ε�����Ȃ��Ȃ��Ă����B�R���̋��Ƀ��[�^���[�N���u�̔肪����B�m�g�j�̎{�݂̈�p�ɁA�H���Ɏg�����Ǝv���鋫�E�����t����B |
| �蕶 | �k��ϑ����� | ���[�^���� | ���E�� |
| �@�ԊO.5�P�������̔�ƃ����[�t �@ |
| �@���R�̎R���ɃP�������̉̔肪����B�蕶�ɂ́u�_�킫��/�_�����₫��/�_������/�������Ђ�/���Ђ���/�Ƃ���/���݁v�ƍ��܂�Ă���B�P�����̖T�ɁA���m�R�̃����[�t�ƕW���W�����Y�����Ă���B���키����ƈ���āA�Â��Ȏ��������Ă���B |
 |
|||
| �f04.7.31 | �f18.7.30 | �f13.9.27 | �f07.9.1 |
| �@55.�u�D�M�����ԓ��D�y���`�D�y�ԊJ�ʋL�O�v�� �@�@�@�@���5��6���ځ@���R�p�[�L���O�G���A�����@�@<�f09.12.8> |
| �@��ʓ������u���R�p�[�L���O�G���A�����v�T�ɂ���l�p���r��ڎw���B�p�[�L���O�G���A���ɓ����Ȃ��̂ŁA�ǂ����悤���Ǝv���ăp�[�L���O�G���A����`���Č���������炵���Δ�͖����B�d���Ȃ��A�r�̒��̓��H�ɓ��낤���Ǝv������A�Q�[�g���܂��Ă����B�Q�[�g�̉��ɒn���̕��X�̎U���������ݐՂ��������̂œ����Č���B��������A�p�[�L���O�G���A�ɍs�������A��͂�Δ�͖����B �@�ĂсA����������߂�ƁA�������Ԃ���E�ɉ��т铥�ݐՂ�����A����`���ƐΔ肪�������B�߂Â��čs���Ƒ傫���u�āv�Ə����ꂽ�Δ肪�������Ă����B�ӂ�͑��䩂ŖK���l�͂��܂苏�Ȃ��悤�������B�Δ�̗�������ƁA����4�N9��30���Ɍ��������悤���B���ɂ͊W�҂̖��O�������Ă���B �@���R�̒n�`������č��ꂽ�D�M�����ԓ��̋L�O�肪�A�����������R�̒��ɂЂ�����ƘȂނ̂ɂ͕s�v�c�ȋC�����������B |
| �p�[�L���O�G���A | ����M�̒� | �Ăƌ@��ꂽ�� | ���� |
| �@���v���o�� �@���Z�̐�y�Ƃ������H���c�̑��ق���Z�ōu�����������ɁA�O�̂g���厖���ƌ������B������āA���Ⴂ�������k�������B���ق͜�R�Ƃ��āA�R�g��������������B�l�ɑ厖�Ȃ̂́u���v�u�w���X�v�u�n�[�g�Hor�w�b�h�H�v�������悤�ȋC������B���̒��ŁA�������{��Ȃ̂ʼn��ƂȂ���a�����E�E�E |
| �@56.�O�c�_��u���{�����L�v���@�O�c�����@�@�@<2013.11.15> |
|
�@�i�q���ׂ��l������n���Ă���ƁA�X�̊Ԃɑ傫�ȐΔ肪�����Č������B�߂Â��Č���ƁA�l�Z��̒��ɂ���B���H��������ʐ^���B�����Ă��������i�O�c1��10����3 �y��@�@�@<�f10.4.3>�j�B |
| �@����25�N10���ɁA���w�̉�����A���O�c�����Ɉڐ݂��ꂽ�B�蕶�́A�Δ�̕\�ʂ̗n�������������A����ĂقƂ�Ǔǂ߂Ȃ������B������Ȃ�������A����������Ă���̂�������Ȃ��Ƃ��낾�����B |
| ���O�c���� | �Δ� | ����� | �蕶�̉�� |
| ���{���r�L �����l�\�l�N�H���� ���{�s�[�k�C����\�ܓ��ߐΎ� ���j�쁜������O�c���_�ꎧ �䁜���������������������� �������D������������������ ���N������������������ �������Ǔc���ׁ����������� �����ԁ������Ǝ����������� �������������������������� ���V���Ӂ����������\���� ���L���������ׁ��L������ �ꌾ���������������������� ����ݑO�c����⽊z �@�@�@�@�@�@�@�@�@�i�R�ߏ����� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�ΐ열�O�ޏ� |
| �@57.�O�c�_��u���{�a����엧���Ձv�L�O���@�O�c1��10����6 �����@�@�@�@<�f09.10.4> |
|
�@�y��̋����猩�Ă��������͖������A�쉈���ɒH���Ă݂�ƁA�l�Z��̒�̒��ɐΔ肪����B���ɓ��炸�A�ʐ^�������B�����Ă��������B �@���ڂȂ̂ŁA�蕶�͓ǂ߂Ȃ��Ƃ��������s���m���B |
| �@�@�@�@�@�@�@��엧���@�L �@�����l�\�l�N������\�ܓ� �吳�V�c�A�������{�a���m�䎑�i���ȃe�k�C ���j�s�[�A���Z�������O�c�_��j�䒓�o�A�� �Z�����A�{��m�ʒu�n���m�ۑO�c�_�ꁜ�q�j �Ύ땽�샒��_�]�A�\�o�T���V�A��엧���� �i�� �@�@�@�@�@�@���a�\�Z�N�����g�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@����@��@�V�� |
| �@58.�k�C�����э�����Ёu�n�����O�\�N�L�O��v�@�@<�f09.10.4> |
| �@�D�M�����ԓ��̃A���_�[�p�X��������A����Ղ��E�Ɍ��āA���������ɋ�����ׂ֍s����������B�I�����낲�뗎���Ă��铹��H��ƁA�����̉��ɍ����Ɏ��ꂽ��א_�Ђ�����B���̗��ɓ��ݐՂ���������`���ɒH���čs���ƁA�O�p�_����̎R���ɉ��т�ѓ��ՂƎv���鏊�ɋL�O�肪�������B �@���ɗыƊW�̋L�O�肾�������ėт̒��������B�߂Â��Č���Ɓu�n�����O�\�N�L�O��v�ƒ����Ă��邪�A���ɒ����Ă��鎚���u���O�ʌM�ꓙ�_�ɏC�m���̍��l���v�Ƃ����ǂ߂Ȃ��B���ɂ́u���a�O�N�\���g�������k�C�����э�����Ёv�ƒ����Ă���B |
| ������� | �L�O���i��~�j | �n�����O�\�N�i��~�j | �L�O��̗��i��~�j |
| �@��̑O�̗ѓ��������܂ő����Ă���̂���Ǝv���A�H���Č���ƁA�����ȑ���z���ĉ��тĂ����B�}�ɉJ���~���Ă����̂ŁA�v�C�ł���������Ԃ��B�A��ɁA��א_�Ђ̓��ŌI�E��������B |
| �@59.���K�ًL�O���@���搼����19����1�@���̐�������@�@�@<2011.5.9> |
| �@�����T���������Ɂu���K�فE���甭�˂̒n�v�̊Ŕ������Ă���B���̐쉈���̍�̊Ԃɉ��т鏬�������֓���ƁA�u�����ۂ�E�ӂ邳�ƕ����S�I72�@���K�ق䂩��̒n�v�̊Ŕ��o�}����B�����̂قƂ�ǂ�����Ă��ēǂނ̂Ɉ��J����B �@�X�ɁA�����̉��ɓ���ƁA�G�]�G���S�T�N�̃W���E�^�����o�b�N�ɐΔ肪�������Ă����B�B�߂Â��Č���Ǝ��K�ًL�O��ƒ����Ă����B�蕶�ɂ͎��K�ق̗R����������Ă������A������ǂ݂ɂ��������B |
| �������� | �����S�I72 | �� | �� |
|
|
| �@60.�h�̎��@���{��2��4����8�@�@�@<�f09.12.28> |
|
�@�������A���C�Ȃ��ʂ��Ă����}���V�����̈�p�ɁA�h�̎�������B�Ŕ��Y�����Ă����̂ŁA�߂Â��Č���B |
| �@�@�h�̎��i�����Z�Z�N�j �����O�\��N�����\���A�y��s�X�n�� �\�˂̑�ЗL��A���̏��䕐�s �̓X�܁E�Z��i�l�\��Ԓn�j�͗ޏĂ� ����~�n���̍��̂����̖ɂĒ����B �吳�l�N�D�y�Ŗ������ݖ������� �����t������A�ݖ��H�ꌚ�݂��A���� �Z��p�n���i�l�\�O�Ԓn�j�ɈڐA���B ���{����E�l�n��ĊJ�����Ɗ����� ��������h�q�ɐՂɋL�O���Ƃ��� �ڐA������̂Ȃ�B �@�@�@������N�\�ꌎ�g�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@���䕐�s |
| �@61.���_�Љ��{�@62.���R�̎O�p�_�@���R�̎R���@�@<�f07.9.1> |
|
�@���R�̎R���ɕ���ł���B �@���{�͖k�C���ň�ԍ������ɂ���B |
| �@63.���p���_�C�X�q���b�e�@���R�̎R�[�@�@�@<�f09.8.22> |
| �@���R�̃��[�v�E�F�C��̃J�[�u�ɃQ�[�g���t�����ѓ�������A���̓����������ƁA�E��Ƀq���b�e�̊Ŕ�����B�E�b�h�`�b�v���~���ꂽ����H��ƃq���b�e�������B�q���b�e�̉��ɂ̓o�[�x�L���[�̘F�ӂ�������B |
| �q���b�e | ���� | �Ŕ� | �o�[�x�L���[�̘F�� |
| �@64.���̕v�w���@���2��6����11�@�r�c�@�O �@�@�@<�f09.12.8> |
|
�@����5���������̎}���ƌ������鏊�ɂ��閯�Ƃ̑O�ɓ�{�̃}�c������B |
| �@�@�@�@�@�@�@�ہ@���@���@�� ���@��@�A�J�}�c�E�N���}�c ���@��@��105�N�i�w�莞�j �K�@�́@�����@ 6.0�l�E����1.3�l�i�A�J�}�c�j �@�@�@�@�@�����@10.0�l�E����1.6�l�i�N���}�c�j �@�����̎��́A�����L�Ғr�c���ꂳ��̑]�c�� �r�c�H�O�Y���A����17�N�L�������瓖�n�ɓ��A���� �L�O�ɐA�������̂ŁA�n��Z��������̕v�w�}�c �ƌĂ��ɂ���Ă��܂��B �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���a60�N5��24���w�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�D�@�y�@�s |
| �@65.���L�O���@���搼����21����3�@�@�@<2011.5.9> |
|
�@���a44�i1969�j�N�ɊJ�݂��ꂽ�L�O�قŁA�J���̎ʐ^��_�@��A�o�y�����y��Ȃǂ��W������Ă���悤���B |
|
�U���H�������P���@�@�@�@�@�肢���@�@�@�@�@�@�k�̒T���K�� |
|
�@��l�̎U���H�L�^ �@2003.2.22�@2007.9.1�@2009.8.9�@2009.9.12�@2009.12.8�@2009.12.18�@2010.4.3�@2010.4.19�@2010.4.22 2011.4.15 |